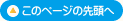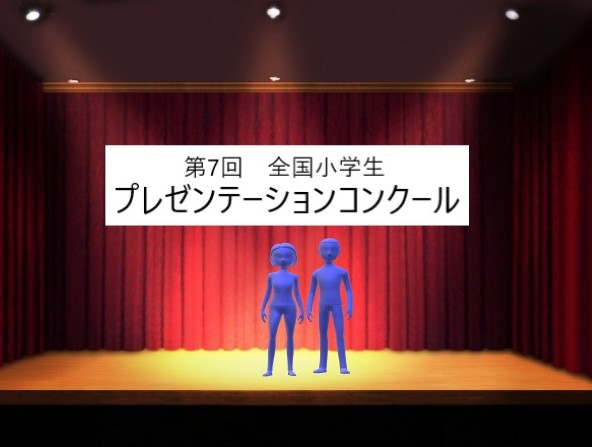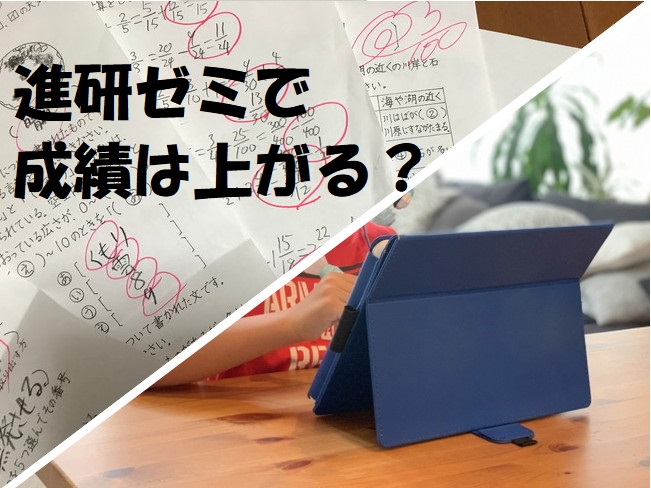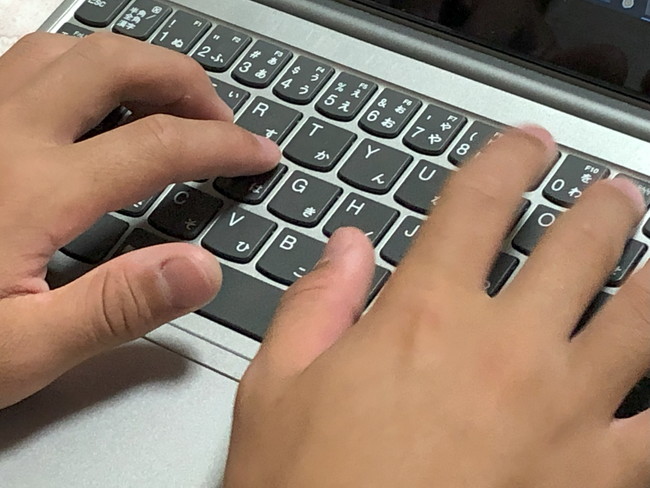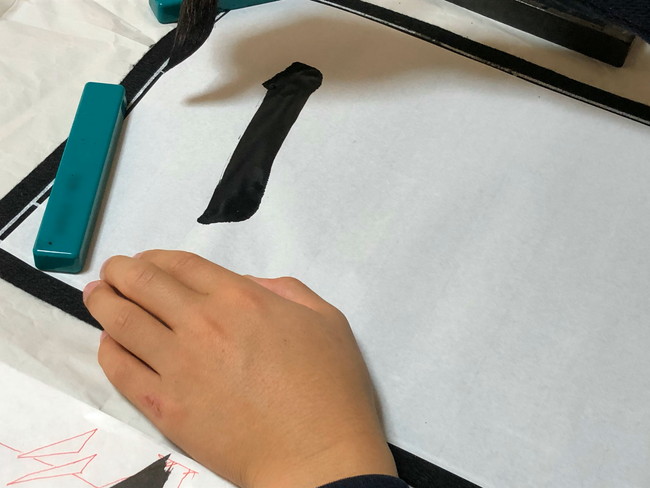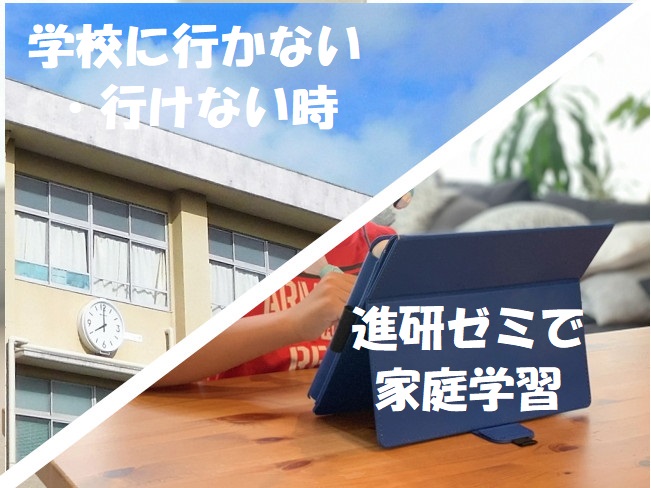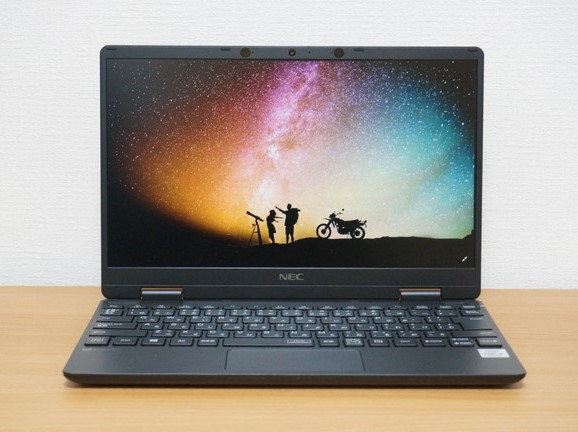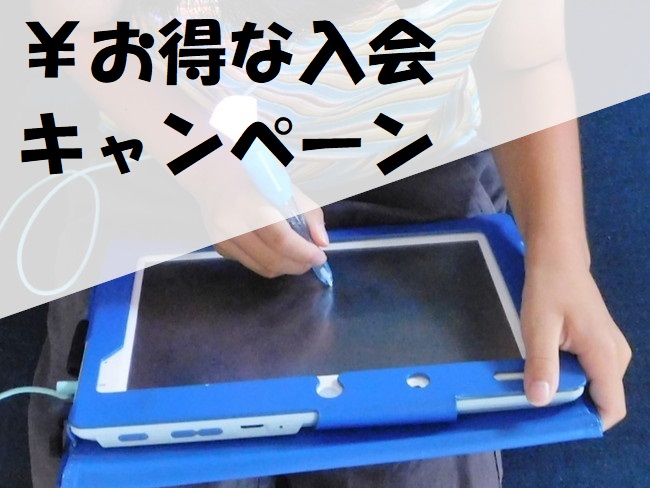小学校のプレゼンテーション学習/気になる指導内容と成績評価

とうとう小学校でもプレゼンテーションの授業が始まりました。しかし、私たち、現在の小学生の親世代は、小学校でプレゼンテーションの授業を受けたことがなく、今の小学生が、どのようなプレゼンテーション授業を受けているのか見当もつきません。また、小学生としてどのようなスキルを身に付けておくべきなのか、通知表の評価がどうなるのか、などわからないことがたくさんあります。
こちらでは、子供を持つ親として気になった小学生のプレゼンテーション学習の指導法や評価法などについてまとめています。
資料の抜粋や説明などがあってちょっと堅苦しいなと思われた方、1分で読める【まとめ】
をご覧ください。
小学校のプレゼンテーション指導/何をどう学ぶか?

プレゼンテーションに関して、学校ではどのような指導をすることになっているのでしょうか?
小学校学習指導要領(文部科学省)によると、小学生で学ぶべきパソコンの基本操作は、合計8つあります(小学校でのパソコン、プログラミング・身に付けるべきスキルとは?)。そのうち、手段を適切に活用して調べたものをまとめたり発表したりする学習活動はその8番めに記載されています。
1) 学習活動を円滑に進めるために必要な程度の速さでのキーボードなどによる文字の入力(=タイピング)
2) 電子ファイルの保存・整理
3) インターネット上の情報の閲覧
4) 電子的な情報の送受信や共有など(=メールの基本操作)
5) 文章を編集したり図表を作成したりする学習活動
6) 様々な方法で情報を収集して調べたり比較したりする学習活動
7) 情報手段を使った情報の共有や協働的な学習活動
8) 情報手段を適切に活用して調べたものをまとめたり発表したりする学習活動
”手段を適切に活用して調べたものをまとめたり発表したりする学習活動”とされていますが、小学校学習指導要領には下記のように記載されており、単に資料を作ったり発表したりすることではなく、パワーポイントやポスターなどを使ったプレゼンテーション学習を子供たちが実践していくことが示されています。
探究的な学習の目的に応じて、本やインターネットを活用したり、適切な相手を見付けて問合せをしたりして、学習課題に関する情報を幅広く収集し、それらを整理・分析して自分なりの考えや意見を
もち、それを探究的な学習の目的に応じて身近な人にプレゼンテーションしたり.......

たったの一例としての紹介しかできませんが、うちの子が通っているK小学校の状況を紹介します。
K小学校の場合---------------------------
【3年生】
プレゼンテーションの授業が開始
【4年生】
プレゼンテーションの授業が本格化
自分の興味のある題材(スポーツ、本、音楽など)から、好きなテーマを選び、パワーポイントにまとめる。
【5年生】
クラスでプレゼンテーション発表会を行う。
地域の名所、博物館・美術館などから好きな場所を紹介する資料をパワーポイントで作成し、クラスで発表する。
【6年生】
学年全体でプレゼンテーション発表会を行う。
校外学習についてグループで話し合って企画作成し、その企画をパワーポイントにまとめて、グループで発表する。
---------------------------
費やす時間は、K小学校の場合、平均すると月に1、2回の授業が行われているようです。学年が上がると増えてくるのかというとそういうわけではありません。また、運動会や音楽会などの行事で忙しい時期は、あまりプレゼンテーションの授業が行われない傾向にあるようです。
小学生のうちから学校でプレゼンテーション学習をする機会がもらえるのはありがたいことです。プレゼンテーションの教育を受けてこなかった私たち親世代と比較すると、子供たちはきっとたくさんのことを学んでくれていると期待できそうですね。
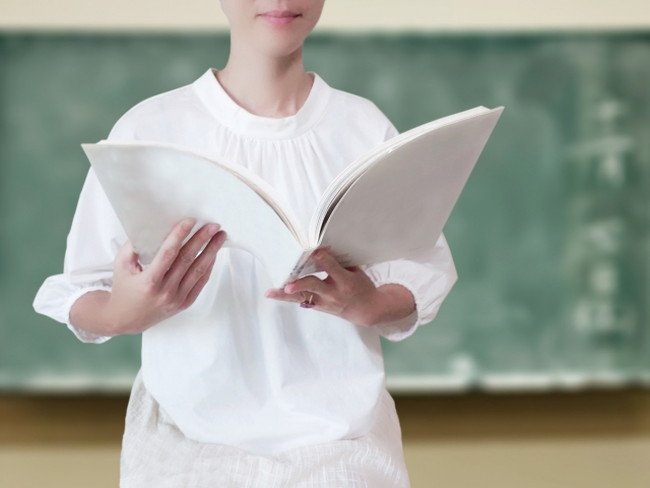
国語や算数は、〇年生でこの漢字を習うとか、〇年生で割り算を習うなど、検定教科書やテストを確認すれば、習得内容がわかります。一方、プレゼンテーションに関しては、教科書やテストもありません。通知表で評価されることもありません。学校の指導で子供たちはどこまで理解し習得できているのか、親が何もしなければ、子供の習熟度を知ることができません。もしかしたら、興味を持って取り組む子とそうでない子のプレゼンテーションスキルの差が大きくなっていくということも考えれます。
現状では、プレゼンテーション学習の指導内容は自治体や学校に委ねられています。 さらに、文部省の資料からは、先生方がどの程度の時間と労力を費やすのか、どういった指導をするのか、教員の育成や研修などといった指導者側の問題も残されていることがわかります。
担当した先生の力量に依存するところが大きいと、学校内でも格差が出てきます。さらに、 学校格差や地域格差が大きくなるということも念頭に置いておかなかればなりません。こういった難しい問題が一朝一夕に解決されることはありません。
このような状況を考慮すると、新学習指導要領をもとにした国からの教育推進、さらなる支援を期待しつつ、私たち親は待っているだけではなく、積極的に子供の状況を把握し、家庭での子供のサポートを考える必要がありそうです。
小学校のプレゼンテーションスキル・成績への影響や評価法

プレゼンテーションスキルは、ビジネスには必須のスキルです。小学生のころから、プレゼンテーションの重要性を認識し、訓練しておけば将来のために役に立つに違いありません。
世には、大人向けに”プレゼンテーションが上手くなる方法”についての指南書や講座が溢れているように、わかりやすいプレゼンテーションをするのは大人でも難しいものです。小学生にはかなり難しい課題だと感じます。
小学校でのプレゼンテーション指導において、”〇年生でここまでできればOK”という目標はあるのでしょうか?

文部科学省の「教育の情報化に関する手引」を調べました。「教育の情報化に関する手引」は、今回の学習指導要領の改訂に対応して作成された、先生や学校など指導者側がみる手引きです。情報教育の目標となる「情報活用能力」とは具体的にどのような能力であるのか、またそれらの能力を子供たちに身に付けさせるために何をすればよいのかについて解説されています。こちらの資料では、児童生徒の発達段階をイメージして5
つの段階で示されています。
「教育の情報化に関する手引」によると、小学生では、ステップ3まで習得することを目標としています。
(ステップ4と5が、中学生と高校生ですが、こちらでは省略しています。)
ステップ 2 (小学校中学年):相手や目的を意識したプレゼンテーションの方法
ステップ 3 (小学校高学年):聞き手とのやり取りを含む効果的なプレゼンテーションの方法
一方、「教育の情報化に関する手引」作成検討会の会議資料 によると、
4年生では、“写真に文字を加えてプレゼンにまとめ発表できる”
5年生では、”アイコンタクトを取りながら相手にわかりやすくプレゼンで発表ができる”
6年生では、”様々な発表形式から自分に適した方法を選び効果的に発表できる”
こちらの手引きを見る限り、プレゼンテーション指導に関して、小学生でもかなり高い目標が設定されていることがわかります。ここに到達できれば大人でも一人前と言えるでしょう。しかし、”効果的なプレゼンテーション”と言われても、具体的にどうすればよいのかよくわからないというのが正直な感想です。
プレゼンテーションというものは、漢字や計算問題のようにこれを覚えておけばOK!というな単純なものではないので、仕方がないと諦めるしかないのでしょうか?

プレゼンテーション学習に関わる目標の達成度はどのように評価されるのでしょうか?
下記は、小学校学習指導要領の抜粋です。
第1に、信頼される評価とするためには、教師の適切な判断に基づいた評価が必要であり、著しく異なったり偏ったりすることなく、およそどの教師も同じように判断できる評価が求められる。例えば、あらかじめ指導する教師間において、評価の観点や評価規準を確認しておき、これに基づいて児童の学習状況を評価することなどが考えられる........
第2に、児童の成長を多面的に捉えるために、多様な評価方法や評価者による評価を適切に組み合わせることが重要である........成果物の出来映えをそのまま総合的な学習の時間の評価とすることは適切ではなく、その成果物から,児童がどのように探究の過程を通して学んだかを見取ることが大事である........
第3に、学習状況の結果だけではなく過程を評価するためには、評価を学習活動の終末だけではなく、事前や途中に適切に位置付けて実施することが大切である。学習活動前の児童の実態の把握、学習活動中の児童の学習状況の把握と改善、学習活動終末の児童の学習状況の把握と改善という、各過程に計画的に位置付けられることが重要である........
今後は、教師一人一人が、児童の学習状況を的確に捉えることが求められる。そのためには、評価の解釈や方法等を統一するとともに、評価規準や評価資料を検討して妥当性を高めること(モデレーション)などにより、学習評価に関する力量形成のための研修等を行っていくことも考えられる........
以上の内容を箇条書きでまとめると、評価に関しては
✔ テストのように数値的な評価はしない
✔ 評価のためには、複数の先生での目線合わせ行う。さらに、自己評価、児童間、地域の人々などの評価を組み合わせる
✔ プレゼンテーションだけではなく、そこに至る過程で学んだことを評価する
ということになりそうです。
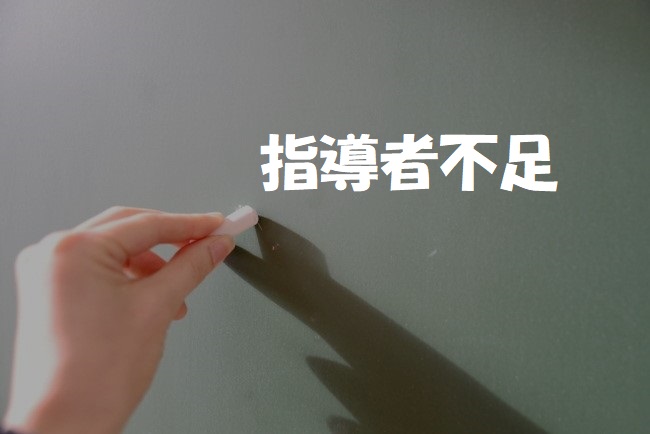
指導者が、児童の学習状況を的確に捉えることが求められ、そのための指導者側スキルアップの必要性についても言及されています。
現在、小学校では、小学1年生が35人以下、また、小学2年生以上は40人以下と定められています。2021年度に、公立小学校のクラスの定員が35人学級になることが閣議決定され、学級編制の標準を5年間かけて計画的に40人から35人に引き下げることになりましたが、それでも、一クラス最高で35人となります。
先生方も研修などを通してスキルアップを行いながら、35人の児童の学習状況を的確に捉えるというのは理想的かもしれません。しかし、先生方が、通常業務に加えてこのような仕事をこなすのは、現実的には難しいように思えます。サポート体制は整いつつあるのでしょうか?
プレゼンテーションスキルというものは、なかなか数値化できないため、目標を設定したり、評価したりするのは難しいものです。小学校学習指導要領に記載のある通り、いくつかの評価方法を組み合わせ、複数の人の目を通して、児童を学習状況を見守りながら評価するということが理想的です。しかし、他の教科の指導を行いながら限られた時間の中で、このような複雑な評価を行うのは先生方の負担が大きいように思います。実際の現場では、どのような評価を行っているのでしょうか?
今のところ、プレゼンテーションに関しては、通知表で評価することにはなっていません。プレゼンテーション学習に力を入れている学校では、フィードバックがあるかもしれませんが、全くフィードバックがないという学校も珍しくないでしょう。
しかし、学校でどのような評価をしているのかわからないから、何のフィードバックもないから、諦めてしまっては、いい結果は得られません。今後さらなるサポート体制、評価方法が整うのを期待しつつ、私たち親は子供の指導者・評価者の一人となって、子供を積極的に見守り、サポートしていく必要があるのではないでしょうか?
小学校のプレゼンテーション指導法・評価法【1分で読めるまとめ】
学習指導要領とは全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるように定められたものです。しかし、プレゼンテーション指導に関しては「小学生からプレゼンテーションについて学ぶ」ということだけが決められているだけで、指導法・評価法は、各自治体や学校、先生方に委ねられており、明確な規定はありません。このように自由度が高い環境では、意欲の高い子だけが学習し、意欲のない子は特になにもしなくてもやりすごせてしまいますので、子供の習熟度に大きな差がつくことになります。
通知表などで評価されることもありませんので、私たち親は、受け身でいると、子供の習熟度について知る機会はないかもしれません。
現時点で私たちができることは、積極的に子供の状況を把握し、家庭での子供のサポートを考えることではないでしょうか?
下記の記事では、小学生のプレゼンテーションスキルアップに関わる練習法や通信講座など、様々な小学生の家庭学習について紹介しています。是非、ご覧ください。
● 「教育の情報化に関する手引」(文部科学省)
● 「教育の情報化に関する手引」作成検討会の会議資料 (文部科学省)
● 【総合的な学習の時間編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説
● 小学校における35人学級の実現/約40年ぶりの学級編制の標準の一律引下げ